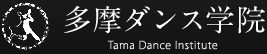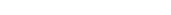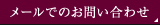クロード・モネ作「散歩、日傘をさす女」という名画がありますが、私は、素晴らしい絵だと思っています。 暑さも真っ盛りの今日この頃、街中を日傘をさして歩いている女性の姿がよく目につきます。 雨の日の雨傘と違って夏の日の日…
学院長ブログ
手の五指を伸ばしましょう
テレビでスポーツや格闘技を観戦していると、つい手に汗を握ってしまったりする場合がありますが、そういう時は、身体に力が入っていて、呼吸が窮屈になっているのです。 気がついたら、手の指を伸ばして身体から力を抜いて、リラ…
小股の切れ上がったいい女
現在では、あまり使われなくなっているようですが、江戸時代あたりには「小股の切れ上がったいい女」という言葉がよく使われていたようです。 辞書で調べると、「和服を着た女性の、足がすらりと長く、粋な体つきであることをいう」…
肩の3軸をずらす
つぎに、肩の部分を説明します。 腰と同じように、左右の腕を動かした時に、3軸が固まっていては、つまり胸椎・胸骨に対して両鎖骨・両肩甲骨が固まっていれば(肩が固い状態)、身体の本体が不安定になってしまいます。 中心軸と左…
腰の3軸をずらす
身体を3軸に分けることが理解出来たら、その3軸をどのように動かすかが問題になります。 最も基本的で重要なことは、中心軸を上へ、左右軸を下へずらすことです。決して、3軸を固めてしまわないことです。 つまり、中心軸と…
身体を3軸に分ける
私たちの身体を2つの部分に分けるとすると、皆さんはどのように分けるでしょうか。 上と下、右と左、前と後、内と外・・・いろいろと考えられますが、多くの方は上と下、つまり上半身と下半身とに分けるのではないでしょ…
3軸運動理論
私はこれまでに、社交ダンスの踊り方として2軸という言葉を使ってきましたが、同じような考え方や言葉は他にもあるようです。 しかし、2軸という言葉は私が知る限りでは、平成15年に京大大学院人間・環境学研究科の小田伸午助教授…
レッスンが終って
学院のホームページがリニューアルされました。 内容はあまり変わっていませんが、以前よりシックに、大人っぽくなったのではないでしょうか。 これからは、写真を多く、記事も増やしていきたいと思っていますので、皆さん、今までと…
言葉について
日本語の語彙(い)の数は50万語以上とされていて、世界でもトップクラスの語彙の多い言語だということです。 これは、世界に対して、日本の文化の誇れる一面ではないかと思います。 しかし、私のボキャブラリーの貧弱さを充分に認め…
下腹筋と腸腰筋の拮抗力
そこで、身体をしっかりと伸ばして動かす為には、下腹筋と腸腰筋をどのようにシンクロさせて使うかということになります。 身体の後面における仙骨に相当するのが前面の下腹筋であり、又、後面における左右の腸骨に相当するのが前面の左…